■■【今回のご質問にお答えのコーナー】■■ 🏠大工や営業マン任せより「設計主導の家づくり」が魅力
こんにちは!
今回も、お悩みにお応えしていきます!
奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。
★★★★★
🏠大工や営業マン任せより「設計主導の家づくり」が魅力
家づくりを考えるとき、多くの方が最初に相談するのは住宅会社の「営業担当者」です。
しかし、本当に満足できる家を建てるには、**「設計士が主導する家づくり」**こそが最も大切です。
大工さんの腕はもちろん重要ですが、
その前に「どんな図面を描くか」「どう暮らすか」を設計段階でしっかり固めることで、
住み心地もデザインも、格段に良くなるのです。
■ ① 営業主導の家づくりには“限界”がある
大手住宅メーカーでは、
最初に対応するのが営業マンであることがほとんどです。
営業担当者は話しやすく親切ですが、
「間取り」「構造」「採光」「動線」などの専門的な判断は、
設計士でなければできません。
そのため、
-
要望が正確に伝わらない
-
標準プランの範囲内でしか提案されない
-
現場で大工さん任せになる
といったケースが少なくありません。
家づくりは“販売”ではなく“設計”から始まります。
ここを間違えると、完成してから「思っていたのと違う…」という後悔につながるのです。
■ ② 設計主導の家づくりは「暮らし方」から始まる
ランドマークが大切にしているのは、
**「家を売る」前に「暮らしを設計する」**という考え方です。
たとえば、
-
洗濯をどこで干すのか
-
子どもの勉強スペースをどう確保するか
-
将来、親と同居する可能性があるか
こうした「暮らし方の設計」を最初に共有し、
その上で建物の形を考えていくのが“設計主導”の家づくりです。
これにより、
見た目だけでなく、毎日の生活動線が自然でストレスのない家が実現します。
■ ③ 設計士が主導すると「予算の使い方」が賢くなる
設計主導の家づくりは、無駄なコストを減らすことにもつながります。
営業主導の家づくりでは、
「オプションの積み重ね」で予算が膨らみがちですが、
設計士は**“コスト配分”を設計段階で調整**できます。
-
光を取り入れるための窓の位置を最小限で効果的に
-
間取りをコンパクトにして施工コストを下げる
-
標準仕様で性能を最大限に活かす
結果として、
**「建築費を抑えつつ、質を上げる」**という家づくりが可能になるのです。
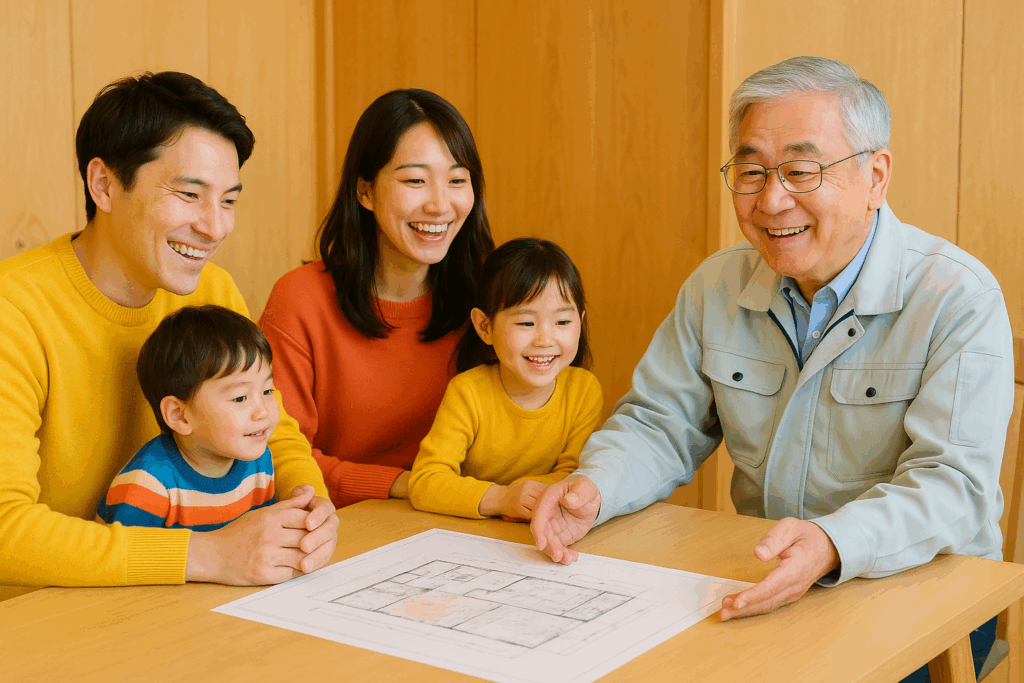
■ ④ 設計士は“構造と暮らし”の両方を見ている
営業や施工が得意な人は多いですが、
設計士は家全体を構造・デザイン・暮らし方のバランスで見ることができます。
たとえば――
-
南向きの大窓が本当にベストなのか?
-
風の抜け道は確保できているか?
-
収納を作りすぎて居住スペースを圧迫していないか?
これらをトータルに考えるのが、設計主導の家づくりです。
図面の1本1本に意味があり、
そこに**「家族の未来の暮らし」**が描かれています。
■ ⑤ 「設計士と直接話せる」安心感
家づくりでは、
「誰に話を伝えたらよいか分からない」というストレスが意外と多いものです。
営業→現場監督→設計→大工…と人が変わるたびに、
思いが薄まってしまう。
ランドマークでは、
最初から最後まで設計士が直接対応します。
そのため、
「意図が正確に伝わる」「判断が早い」「迷いがない」。
結果として、理想の家がブレずに完成します。
■ ⑥ 「設計主導の家」は、完成後に差が出る
家を建ててから数年経つと、
設計の差がはっきり現れます。
動線の良い家は、家族が自然と集まり、
断熱・遮熱性能が高い家は、光熱費が安く保たれます。
見えない部分まで丁寧に設計されている家は、
長く住むほど“本物の価値”が出る家です。
ランドマークが提案する「設計主導の家」は、
単なるデザイン住宅ではなく、暮らしを科学した設計住宅です。
🌸
-
営業主導よりも「設計主導」で家を考える
-
暮らし方から設計を始めることで“後悔のない家”に
-
設計士はコスト配分と快適性の両立を図る
-
設計段階で品質が決まり、住んでから本当の差が出る
家づくりは“誰が売るか”ではなく、“誰が設計するか”で決まります。
ランドマークでは、設計士が直接お客様と向き合い、
「暮らし方」から家をデザインしています。
建てて終わりではなく、建ててから始まる快適な暮らしを設計する――
それが、設計主導の家づくりの魅力です。
次回の【ご質問にお答えのコーナー】でも、
皆さまのお悩みを解決するためのたくさんのヒントをご紹介していきます。
ぜひ、皆さまのご質問をお寄せください!
↓ ↓ ↓


